タイトルのネタ元は、これらの本↓です。
『司法試験機械的合格法』
『東京大学機械的合格法』
中高生時代、一番尊敬する人物はこの本の著者であった、
子供の頃から一風変わり過ぎていた男、
クマガワ(@Kumagawa_Pro)です! 苦笑
さて、当ブログのメインテーマは、2020年2月現在、英国勅許公認会計士(ACCA)という資格に関するお話でございます。
そして、資格を題材にしたサイトの使命として、「どのように勉強すればよいのか?」についての話題は避けて通れないでしょう。
というわけで、今回はACCAの勉強方法をテーマにお話ししていきたいと思います。
今現在、私はFAに合格済みで、ABとMAの合格に向けて学習を進めている最中です。そこで、ひとまずは、
基礎知識科目 (AB,MA,FA) + LW の4科目 の勉強法
について、語っていきます。
いきなり結論:テキストを読んで、問題集を繰り返し解きましょう!
AB、MA、FA、そしてLWの4科目は、すべてオンデマンドのコンピューター試験で実施されます。
出題形式は、選択式、穴埋め式、計算問題等、短答式の問題のみで、論述式の設問は1問もありません。問題の難易度も、あまり難しくないです。
このタイプの試験においては、いろいろと勉強法を語ってみたところで、結局のところ、
① テキストを読む。
② 問題集を繰り返し解く。
という方法に集約されることでしょう。
まさに、「王道の勉強方法」です。異論はほとんど無いと思います。
実際に私も、このような勉強法でFAの試験を突破し、ABとMAにも挑もうとしております。
実際の体験談 ~クマガワがFA合格までに行った勉強の手段や量
「王道の勉強方法」を紹介しただけでは、正直言って、この記事に何の面白味も価値もございませんよね…… 苦笑。
そこで、私クマガワがFAの試験に合格するまでに実際に行った勉強の内容について、詳細かつ具体的にご紹介したいと思います!
使用した教材
BPPというイギリス現地の予備校が出版しているテキストと問題集を使用しました。
BPPの教材は、ACCA協会公認の内容(ACCA Approved Content)になっているとの事です(他にもKaplanという予備校が、“ACCA Approved Content”の教材を発行しています)。
【テキスト】※リンクは古いバージョンのものですが……
【問題集】※こちらも古いバージョンのものですが……
問題集は、この1冊で十分だと思います。結構な量の問題数が収録されていますので(500問以上です)。
もし1冊で不安なら、他の予備校の問題集を購入するのもいいと思います。
あるいは、BPPの教材は、購入特典として、BPPのWebサイトにアクセスし、オンラインで追加の問題を入手することができます。そちらを利用するもいいでしょう。
(他の予備校の問題集にせよ、BPPの購入特典のにせよ、私はどちらも使用しませんでしたが……)。
テキストも、この1冊で十分です。他の予備校のテキストは不要でしょう。
何しろ、まるで電話帳みたいな分厚くて大きい教科書ですので 苦笑。その分、網羅性は完璧なはずです。試験範囲に含まれているのにテキストには書かれていなかった、という項目はほとんどないでしょう。
ただ、自分の理解度に応じて、日本語の参考書を適宜追加で利用するはありだと思います。
実際に私は、連結会計の基本的な部分がうろ覚えになっていたので、以下の書籍を購入して目を通しました。
『図解&設例 連結会計の基本と実務がわかる本』
※「基本編」「応用編」「開示編」の3章構成となっていますが、FAのための学習としては、最初の「基本編」だけを読めば十分です。
※当たり前ですが、この本は日本の会計基準をベースに書かれています。ご使用の際はIFRSとの違いにはくれぐれも注意して下さい。特に、のれんの処理方法が完全に異なっています(それ以外の項目は、「基本編」の範囲であれば、日本基準とIFRSとに大きな違いは見られません)。
勉強の量や時間
まず、テキストを2周読みました。
BPPのテキストには「Quick Quiz」という章末問題が付いているのですが、そちらも『解くのではなく読む』感じで目を通しました。一方、「Practice Question Bank」という練習問題集も付属しているのですが、そちらはきちんと解いて勉強をしました。
次に、問題集も2周しました。
なお、本の最後の方に模擬試験(Mock exam)が2回分収録されているのですが、時間の都合上、そちらは手を出しませんでした…… 泣
最後に、試験直前の時期は、ひたすらテキストを流し読みしておりました。
「あ、ここの部分、あの問題で訊かれていたなぁ」
「あ、ここの部分、理解が不十分だったな……」
「あ、ここの部分、ブログのネタになりそう!」(笑)
という感じに、『気付き』をできるだけ多く発見して、テキストの内容の理解を可能な限り完璧に近付けていく、というイメージです。
勉強期間は大体1か月半ほどでした。
勉強のペースとしては、平日は朝に1~2時間ほど勉強し(私、かなりの朝型人間なんです!)、休日は0~5時間ほど勉強するという、比較的気楽な感じで進めておりました。
注意点(特に、クマガワの前提知識の面)
以上のような方法で学習を行えば、誰でも必ずFAの試験に合格できるものでしょうか?
答えはもちろん「NO」でございます。
人それぞれ前提となる知識や能力が違いますので、合格までに必要な勉強の量も、当然人によって変わってきます。
そこで、参考情報として、勉強前の時点における私クマガワの“スペック”をお伝えしたいと思います。
会計の知識
公認会計士試験の短答式試験(≒一次試験)に合格した経験があります。レベルとしては、「簿記1級に合格したのと同じくらい」というイメージでしょうか。
また、IFRSや国際会計に関する本も、勉強前の時点で既に何冊か目を通しておりました。
英語力
TOEICは900点オーバーです。
特に、Readingはほぼ満点の490点でした。
その他
学歴は某有名私大の上位学部出身です。
……と、なかなかの“高スペック”な状態からのスタートでした(自分で言うのも照れ臭いですが 汗)。
ただ、私が極めて有利な条件を備えていたことを差し引いても、
『テキストと問題集を2周ずつ』という勉強量は、
多くの方にとって、FAを突破するには十分なものだと考えています。
といいますのも、私自身は、この量の勉強をして、「50点取れれば合格の試験を、89点で合格」しているんですよね。
とすれば、私みたいに“中途半端に高度な会計の知識や英語力を備えている”ような人でなくとも、89点は無理にしたって、さすがに50点は取れるでしょう、と推察できるからです。
テキストを読むコツ
さて、先ほど私、BPP発行のテキストのことを「まるで電話帳みたいに分厚くて大きい」と申し上げました。
そうなんです。
総ページ数が500を超えているだけでなく、サイズがA4判で写真集とかと同じなんです!
(なお、調べてみますと、BPPだけではなく、Kaplanの方も似たような感じみたいです)
こんな「存在感が半端ない」テキストですので、読み込みをするにしても、頭から終わりまで一つ一つ丁寧に読んでいくわけにはいきません……。まして、すべて英語で書かれているのですから……。
そこで、私が個人的に実行していた、ACCAのテキストを手早く読むコツを皆様にお伝えしたいと思います! 是非ともご参考にして頂ければ幸いです。
「読む」のではなく、「情報を拾い上げる」というイメージで!
テキストの文章を頭から淡々と「読む」のではなく、
未知の内容や新しい発見、あるいは興味が惹かれる解説や視点等を「拾い上げる」ということを常に意識して、テキストに目を通しておりました。
そもそも、試験勉強とは、『合格に必要な知識やスキルと、今現在の自分とのギャップを埋めていく』過程だからです。自分にとって新しい知識や発見であったり、あるいは既存の知識・スキルを拡充できる情報でなければ、習得の必要はありません。
ですので、既に内容を知っていて、かつ、新しい発見も知的好奇心の刺激も期待ができなさそうな箇所については、ガンガン読み飛ばします。
たとえば、固定資産の減価償却(Depreciation)の論点を例に挙げてみましょう。
テキストを読んでいて、
・『定額法』って、英語では“straight line method”っていうんだ!
・『定率法』は、“reducing balance method”なのか!
などと思えば、まさに未知の知識、新しい発見です。
しかしながら、「定額法」や「定率法」そのものは、簿記・会計における基本中の基本の項目です。ACCAの勉強を開始した時点で既にその内容を完璧に理解している人は、数多くいらっしゃると思います。
そういう方々にとっては、「定額法」や「定率法」の内容を解説している部分は、バッサリと読み飛ばしても何も支障はないわけです。
ただ、もし、固定資産を期中に取得したり処分した場合の細かい処理がうろ覚えに
なっているようであれば、そこを説明している箇所については、目を留めてしっかりと読み込んでいく価値はあるでしょう。
『設例』や『例題』は基本的に読み飛ばす
BPPのテキストでは、処理や理論や概念の抽象的な説明をした後に、『設例』(Example)や『例題』(Question & Answer)が頻繁に挿入されます。
受験生の理解に配慮した親切な設計なのだとは思いますが、これらが数多く入っているせいでページ数が膨れ上がってしまっているのも事実です 苦笑。
いずれにしましても、少なくとも私は、これらの『設例』や『例題』をほとんど読み飛ばしておりました。
というのも、これらは「具体例を通じて、理解を深める」ために挿入されているからです。
であれば、それは後々、問題集を繰り返し解く過程の中で実現した方が、はるかに効率が良いです。知識のインプットをする時間とアウトプットをする時間はしっかりと分けた方が、勉強が進めやすいですよね?
ただし、抽象的な説明だけでは理解がチンプンカンプンな項目については、設例や例題にまで目を通す価値は大きいと思います。
たとえば、先ほどの減価償却の例でいえば、そもそも「定額法」や「定率法」の内容を一切知らない人にとっては、抽象的な説明を読むだけでその意味を完全に理解することは、非常に難しいと思います。抽象的な解説の後に続く設例や例題を通じて、“straight line method”や“reducing balance method”が具体的にどのような計算をするのか、実際に体験して学び取る必要があるでしょう。
文章を丸々読む必要がない箇所は、ざっと目を通して「拾い読み」!
上記の他にも、
テキストの文章を全部しっかりと読み込む必要は乏しいと思われる箇所ついては、
ざっと目を通すだけにとどめて、太字の部分やキーワードだけを「拾い読み」しておりました。
そのような箇所は、細かいところまで詳細に記憶をする必要までは無かったり、
あるいは、ゆくゆくはきちんと記憶する必要があったとしても、文章を「読む」だけでは覚えることが困難なため、問題を「解く」過程で頭に定着させる必要があるからです。
たとえば、
「○○の特徴とは……」とか、
「△△のメリットとデメリットはそれぞれ……」といった感じの『箇条書き』の部分については、ほとんどの場合、それぞれの項目名や重要な語句だけに目を留めれば十分でしょう。
「○○」や「△△」の内容から、特徴やメリット・デメリットといった事柄はある程度推測ができるからです。
また、ひたすらに細かい説明が続いているような文章についても、流し読みをするか、いっそ読み飛ばしてしまいましょう。律儀に熟読をしたところで、どうせ読むだけではほとんど頭には残らないからです。
さらに、たくさんの項目がリストアップされていて、それぞれに説明書きが付いているような箇所についても、「流し読み」や「拾い読み」の必要性は大きいと思います。リストアップされている全ての項目について説明の細部まで記憶するのは、とても現実的とは言えないからです。
今回はここまでです。
ご閲読ありがとうございました!
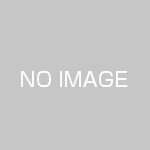

こんにちは。
受験制度や勉強方法等につき、有益な情報を提供頂きありがとうございます!
クマガワさんのお陰でACCAに挑戦する決意が固まりました。
文章もわかりやすく、本当に助かっております!
これからも更新を楽しみにしています:)
Sさん、はじめまして。
お褒めの言葉、大変感激です!
誠にありがとうございました。
当ブログを通じて実際にACCAの受験を決心された方がいらっしゃるというのは、本当に嬉しい限りです 泣。
個人的には、ACCAは、USCPA以上に有用性や将来性が高いと考えております。
そのような将来有望な資格を、まだ日本であまり知られていないうちに取得して、
“先行者利益”をお互いにがっつりと享受してまいりましょう!
今後ともよろしくお願い申し上げます。